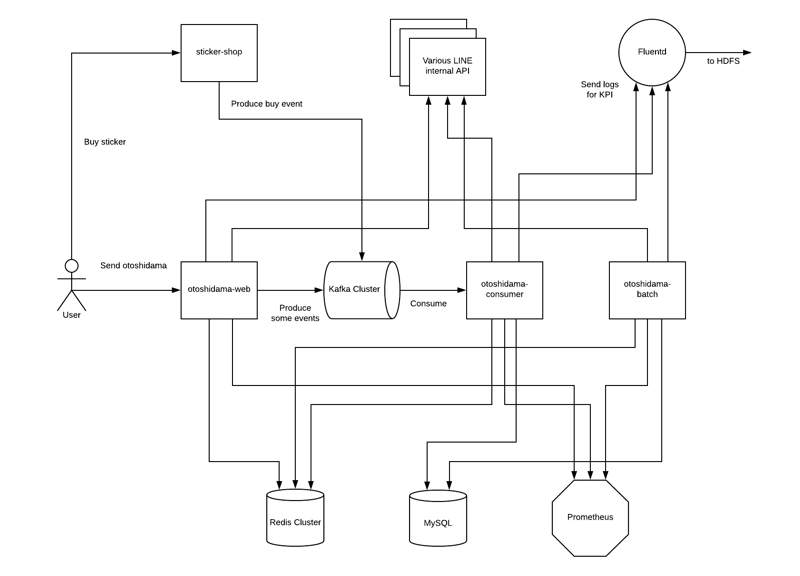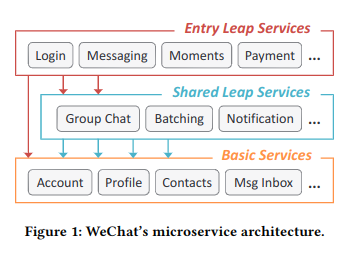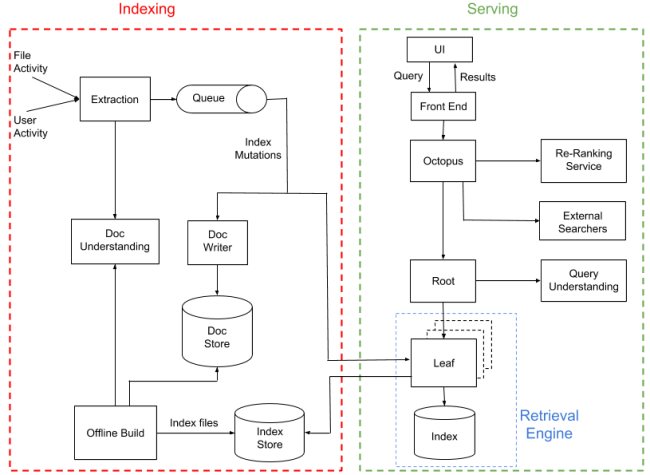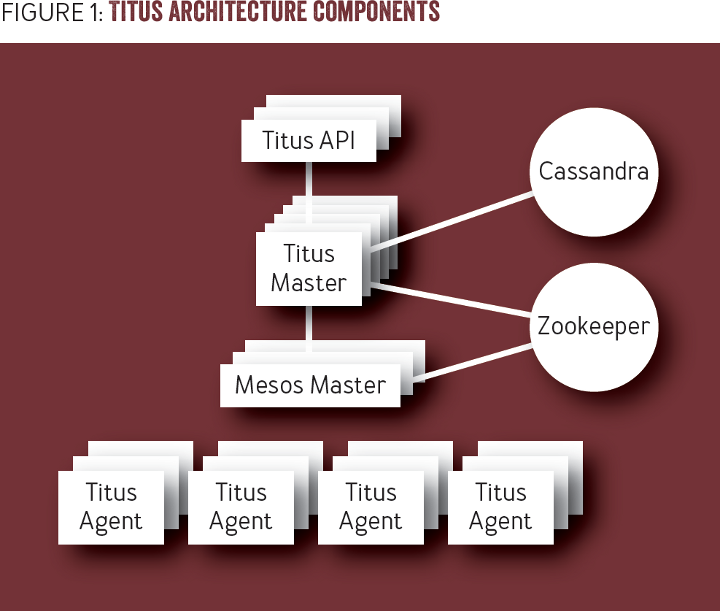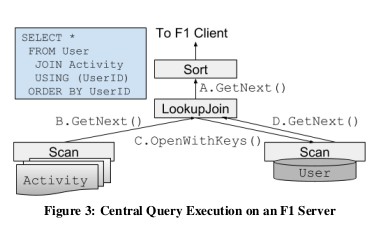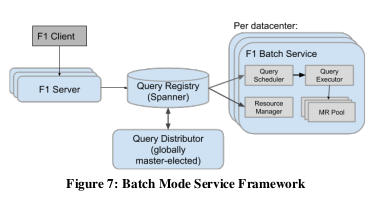はじめに
分散ストレージであるCephについての論文を読んだので紹介します。
最近CybozuのNecoプロジェクトが始まり、面白そうなことをやっているな、と思っていたたところ、Cephについてのブログが出ました。
これを読んで、「Ceph読んでみたいな」と思ったので、理解の足がかりになるかなと思い論文("Ceph: A Scalable, High-Performance Distributed File System")を読みました。
ただし、この論文は2006年に発表されたもので、当時のCephの概要について説明されたものです。
現在の実装とは大きく違うと思います。
たとえば、この論文では「CephはEBOFSという独自ファイルシステムを採用している」とあるのですが、GitHubにはそのようなものは存在せず、2009年ごろに "osd: do not use ebofs"というコミットとともに削除された形跡が伺えます。
それでも、分散ストレージは「自分で作ってみたいシステムランキング」の上位にあるものなので興味深く読みました。
また、論文に出てくる「CRUSH」と「RADOS」はデータの配置と冗長化という、分散ストレージに欠かせない仕組みで、Cybozuのブログを読む限り今も現役なようです。
Cephについて
Ceph自体の説明については、
Cybozuの記事にまとまっているので、そちらが参考になります。: https://blog.cybozu.io/entry/2018/12/13/103039
公式: https://ceph.com
ちなみに、CNCFのIncubating ProjectになっているRookもCeph連携をしています。
論文の概要
"Ceph: A Scalable, High-Performance Distributed File System"では、Cephにおける
- メタデータの管理
- データの管理
- クライアントとサーバーの関係
という、おおよそCephの全体像を書いています。
簡単にまとめると、
Cephは
で構成されていて、クライアントはこの2つのクラスタに問い合わせることでファイル情報や内容をやり取りします。
MDSクラスタの大きな特徴は、「ファイルの位置情報」を保管せずに、計算によって対象ファイルを保持するOSDがわかるということです。
また、OSDクラスタは冗長、耐障害を考慮された設計です。
※ OSD(object storage devices)とは、ディスク(またはRAID)と、それに付随するCPU・ネットワーク・キャッシュを含むデバイスの呼び方です。長いですが、「ファイルコンテンツの一部を持ったデバイスをOSDというだな」という理解で十分だと思います。
以下、詳細です。
System Overview
この章は、Ceph全体についての説明です。次章以降、各機能が説明されます。
メタデータの分離
Cephでは、open, renameなどのメタデータに対する操作はメタデータサーバー(MDS)で一括管理されていますが、read,writeのようなIO操作はクライアントとOSDが直接通信するようになっています。
また、データがどのOSDに格納されているかという情報はメタデータサーバーでは管理していません。その代わりに、CRUSHを使うことで場所が計算できるようになっています。
メタデータの動的管理・分散管理
メタデータに対する操作はCeph全体の負荷の半分にもなる可能性があるので、メタデータを効率的に管理したいところです。そのために、Dynamic Subtree Partitioningという手法を使用しています。
RADOS (Relaiable Automatic Distributed Object Storage)
Cephは数千を超えるデバイスを持つシステムなので、以下のことが想定されます
- デバイスが追加、削除される
- 故障が頻繁に起こる
- 大きなデータが追加・移動・削除される
なので、Cephはデータのmigration,replication,failure detection, failure recoveryの機能を持っています。(詳細は後述)
クライアント操作から見る Ceph
capability
クライアント操作時には、"capability"という操作許可が各クライアントに発行されます。
例えば次のようなcapabilityの移動があります。
read時:
クライアントがread用にopen操作をMDSに要求すると、MDSがreadのcapabilityを与える。
capbilityを与えられたら、クライアントはメタデータ情報を使って、OSDクラスタへアクセスして、データを取得する。
write時:
writeのためのopenの場合には、writeのcapabilityを与える。
その後にクライアントはデータを変更して、closeする。
close操作の時に、MDSはファイルサイズを更新して、capabilityを破棄する。
同期
POSIXでは、読み込み時には書き込み済みのデータを読み込むこと、書き込みはatomicであることを要求しています。つまり、操作は発生順(order of occurrence)に結果を持つことを要求しています。
しかしCephでは、「複数書き込む場合」や、「書き込みと読み込みが同時に発生した場合」には、キャッシュ読み込みとバッファ書き込みのcapabilityが取り消されて、各操作の同期が強制されます。
この方法は、同期IOになるので遅くなりますが、通常のユースケースでは読みと書きが同時に起きることは少ないので、許容できると判断しています。
ただし、許容出来ない場合に備えて一貫性を犠牲にする選択肢も有るようです。
名前空間に関する操作
名前空間に関する「読み(readdir, statなど)」、「書き(unlink,chmodなど)」の操作はMDSに対して行われますが、ロックはありません。これは、シンプルさと最適化を求めた結果だそうです。
例えば、ls -lのようなreaddir+statの操作はよく実行される操作ですが、巨大なディレクトリに対してはパフォーマンスキラーです。
なので、デフォルトではキャッシュが使われます。
そのせいで、一貫性が損なわれますが、パフォーマンスのためには歓迎される犠牲だとして採用しています。
動的に分散されるメタデータ
Cephのメタデータは分散されつつも動的に場所が変わり、以下の特性があります
- 各ディレクトリのコンテンツは同一のOSDクラスタにある
- MDSに配置されるデータはアクセス量に従って動的に変化する(どこかのMDSにアクセスが偏る場合は、一部のディレクトリを別のMDSに移動します)
- メタデータの一貫性のポリシーは、security(ownerやmode),file(size,mtime),immutable(inode number, ctime, layout)の3種類存在し、目的に適したものを使っている。
- 大量のアクセスが同一のディレクトリやファイルに来た場合には、レプリケーションを拡大して、クライアントにレプリケーションへアクセスするように指示する
Distributed Object Storage
クライアントやMDSにとって、OSDクラスタは論理的に一つのストレージであるとみなして扱います。
それを実現するために、以下の工夫をしています。
CRUSH (Controlled Replication Under Scalable Hashing)
ファイルはobjectに分解され、objectはPG(placement group)というグループに割り当てられます。PGはCRUSHを使用して、各OSDに割り当てられます。
CRUSHでは、PGとPGに紐づくOSDのリストがあればデータを持つOSDがわかるようになっています。
この仕組みのおかげで、クライアントやMDSは独立して保存場所を計算することができ、メタデータが持つ情報の更新が少なく済むようになっています。
つまり、CRUSHでは、distribution(どこにデータを置くべきか)とlocation(どこにデータが有るか)の問題を同時に解決しています。
レプリケーションとデータ保全
データは複数PGにレプリケーションされます。
クライアントがプライマリPGのOSDにデータを送ると、対象のOSDは受け取ったデータをレプリケーションにも流して、待機します。
そして、レプリケーションの書き込みが終わってから、クライアントに完了を知らせます。
こうすることで、複数デバイスへの書き込みが保証されます。
Failure detection
ディスク障害などはODSから障害を通知しますが、ネットワーク障害の場合には各OSDのピアが生存確認できなくなった時に、中央に報告が上げられます。
そして、中央がシステム障害なのか一時的なものなのかを判断します。
Cephにはdownとoutの2つの障害状態を用意していて、OSDが通信できなくなるとdownとなりprimaryから外されます。そのままdownの状態が続くようだと、outの状態に遷移してPGには別のOSDが割り当てられます。
このように状態をもつことによって、(停電でOSDの半分がダウンするなど)大規模な障害が起きた時に状態を"down"に留めることによって、大規模なデータの再配置を避けることができるようになっています。
OSDクラスタ情報の更新
Cephの持つクラスタ情報がOSDの追加や削除によって変更されると、各OSDは自身の情報との差異に気づき次第、OSDの「あるべき姿」へと変化します。(「あるべき姿」になるために、プライマリの変更やデータの移行などが発生します)
このように、各OSDは独立して変化するので、あるOSDが落ちた場合には、影響を受けた各PGは並行して復帰します。
EBOFS (Extent and B-tree based Object File System)
Cephでは、メタデータとデータのatomicな操作が出来なかったので、ext3(古い!)のような既存のファイルシステムは使わずにEBOFSというものを作ったそうです。
EBOFSは以下の特徴を持ったファイルシステムです。
- atomic transactionをサポートすると同時に、ディスクへの書き込みは非同期に行われる。
- (既存のファイルシステムが時間を開けるのに対して)ディスクへのflushは積極的にスケジューリングされ、IO操作が不要になったときにはキャンセルすることもできる。
- オブジェクトのディスクへの配置、block allocation, index collectionには、B-treeが使われている。
終わりに
以上、"Ceph: A Scalable, High-Performance Distributed File System"の内容でした。
今回の記事のように、このブログではプログラムを作る時の参考になることを書き続けるつもりです。
もし興味があれば、twitterやブログのフォローしていただけると嬉しいです。